寄席の舞台で観客を魅了してきた紙切り芸の名人、林家二楽(はやしや・にらく)さん。
繊細な手さばきで、わずか数分のうちに物語を描くような紙のアートを作り出すその技は、まさに“寄席芸術の粋”と呼ばれていました。
しかし、2025年9月27日、林家二楽さんは尿管がんのためこの世を去りました。
享年58歳。あまりにも早い別れでした。
この記事では、彼の死因や経歴、本名、家族構成、そして紙切り芸への情熱を、
温かく、そして丁寧にたどっていきます。
■ 林家二楽のプロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 芸名 | 林家 二楽(はやしや にらく) |
| 本名 | 山崎 義金(やまざき よしかね) |
| 生年月日 | 1967年8月23日 |
| 没年月日 | 2025年9月27日(享年58歳) |
| 出身地 | 埼玉県春日部市 |
| 職業 | 紙切り芸人(落語協会所属) |
| 師匠 | 二代目 林家正楽(実父) |
| 家族 | 父:二代目林家正楽、兄:三代目桂小南、息子:林家八楽 |
| 出囃子 | 琉球節 |
| 活動期間 | 1989年〜2025年 |
| 主な受賞 | 国立演芸場花形演芸大賞・銀賞(2002年)、金賞(2005年) |
■ 出身と家族 ― 名門芸人一家に生まれる
林家二楽さんは1967年、埼玉県春日部市に誕生しました。
父は紙切りの名人として知られる二代目 林家正楽師匠、
兄は落語芸術協会所属の三代目 桂小南師匠という、まさに芸の家系に生まれたサラブレッドです。
家庭では芸に関する話題が絶えず、幼い頃から寄席や落語会の空気に親しんできたといいます。
子どもながらに「芸人の世界が当たり前」という環境の中で育ち、
自然と芸の道へ進むことを志すようになりました。
■ 師匠は父・二代目林家正楽 ― 紙切りの世界へ
1989年、21歳のときに実の父・二代目林家正楽に弟子入り。
同年、「林家二楽」を名乗り、紙切りの修業を本格的にスタートさせます。
修行時代は厳しかったといいます。
紙の持ち方、ハサミの角度、観客との間の取り方――。
父は一切の妥協を許さず、「芸は目と心で盗め」という教えのもと、
二楽さんは黙々と腕を磨いていきました。
1991年7月、鈴本演芸場で父と共に初高座を務め、
華々しく寄席デビューを果たします。
以降、持ち前の明るさと確かな技術で人気を集め、
「父譲りの手さばきと、息子らしい遊び心を融合した紙切り」として評判を呼びました。
■ 紙切りの枠を超えた活動 ― 音楽との融合や教育活動も
1990年代には、芸の幅を広げるために多方面へ挑戦。
1993年には若手落語家たちと音楽バンドを結成し、歌やダンスを交えたステージを披露しました。
また、紙切りを体験できる「おやこ紙切り教室」を立ち上げ、
子どもたちに芸の楽しさを伝える活動にも積極的でした。
さらに、クラシック音楽とのコラボレーションや、海外での文化紹介にも携わり、
2006年からはアメリカ・ミドルベリー大学夏期日本語学校に文化講師として招かれ、
紙切りを通して日本の伝統芸能を紹介する役割を担いました。
寄席の枠を超えた活動は、紙切り芸の新たな可能性を切り開いたと高く評価されています。
■ 紙切り芸の魅力 ― 一瞬の切り絵に込める物語
紙切り芸とは、観客のリクエストに応じて即興で紙を切り、
数分のうちに見事な作品を作り上げる寄席芸のひとつです。
林家二楽さんは、その手際の良さに加え、
観客との会話を楽しみながら形を作るライブ感こそが魅力だと語っていました。
ハサミが紙を走る音、観客の笑い声、そして最後に現れる一枚の絵。
それらが一体となって完成する瞬間は、まるで舞台芸術のような美しさがあります。
二楽さんの作品には、人の温もりやユーモアが宿っており、
観客の「笑顔が芸の完成形」として、毎回真剣にステージに立っていたそうです。
■ 尿管がんとの闘い ― 病気と向き合いながらの高座
2024年1月、鈴本演芸場で行われた「落語協会百年興行 三代目林家正楽一周忌追善興行」において、
林家二楽さんは主任を務める予定でした。
しかし初日前日に体調を崩し、緊急入院。
一時は高座を休むこととなりましたが、
数日後には見事に復帰を果たし、観客の前で元気な姿を見せました。
実はその頃から、尿管がんとの闘病が始まっていたといわれています。
体調が優れない中でも、「舞台に立てる限りはやり続けたい」と話し、
最後の高座となったのは2025年8月11日、鈴本演芸場でした。
翌月27日、静かに息を引き取ったと落語協会が発表。
葬儀は近親者のみで執り行われたとのことです。
■ 家族構成 ― 父・兄・息子も芸人一家
林家二楽さんは、まさに芸の血筋を受け継ぐ一家の一員でした。
- 父:二代目 林家正楽(紙切り師)
伝統的な技を守りつつ、寄席の人気者として長年第一線で活躍。
息子である二楽さんの師匠でもあり、芸の礎を築いた存在。 - 兄:三代目 桂小南(落語家)
落語芸術協会に所属し、全国各地で公演を続ける実力派。 - 息子:林家八楽(紙切り師)
父・二楽の弟子として芸を継承。現在は寄席やイベントで紙切りを披露しています。
このように、親子三代で芸を受け継ぐ林家一門は、
日本の伝統芸能を守り続ける貴重な存在といえるでしょう。
■ 妻(嫁)について ― 家族を支えた良き伴侶
妻に関する詳細な情報は公表されていませんが、
関係者の話によると、長年家庭を守り、
病気療養中も二楽さんを支え続けたといわれています。
芸人という不規則な生活の中、
支える側の努力なくして活動は続けられません。
夫婦の信頼関係があったからこそ、
彼は最後まで芸人として舞台に立ち続けることができたのだと思われます。
■ 受賞歴と功績
林家二楽さんは、数多くの舞台に立ちながらも常に挑戦を忘れず、
その功績は高く評価されています。
- 2002年 国立演芸場花形演芸大賞 銀賞
- 2005年 同賞 金賞受賞
寄席芸の世界では珍しく、親子揃って大賞を受けたことでも話題になりました。
また、紙切りを題材にした書籍や挿絵の提供など、
芸を通じて文化発信にも積極的に取り組んでいました。
■ 林家二楽の人柄 ― 温厚で観客思いの職人
関係者や弟子たちは、口をそろえて「優しい師匠だった」と語ります。
後輩の指導にも決して怒鳴ることはなく、
「焦らず、自分のペースで切ればいい」と励ますタイプ。
舞台裏でも常に笑顔を絶やさず、
観客や仲間、スタッフへの感謝を忘れない人物でした。
その温かな人柄が、彼の芸にも滲み出ていたのかもしれません。
■ まとめ:紙切りに人生を捧げた職人芸人
- 本名は山崎義金、埼玉県春日部市出身。
- 父・二代目林家正楽に師事し、1989年に紙切りの道へ。
- クラシックや教育活動にも力を注ぎ、芸の幅を広げた。
- 2025年9月、尿管がんのため58歳で逝去。
- 息子の林家八楽がその芸を継承中。
林家二楽さんは、
「芸は命。命ある限り切り続ける」という言葉を実践した人でした。
彼のハサミが刻んだ一枚一枚の紙は、
今も多くの人の心に笑顔と感動を残しています。

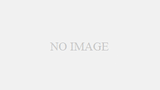
コメント