2025年11月21日、福岡国際センターで行われた大相撲九州場所13日目。この日最も注目を集めたのは、2敗で並ぶ二人の力士――横綱・大の里と、大関昇進を狙う関脇・**安青錦(あおせいにしき)**の直接対決だった。
まさに優勝争いの行方を左右する一番。この勝負においては、土俵際で非常に微妙な攻防が繰り広げられ、ファンや専門家の間で「判定は適切だったのか?」という議論が巻き起こっている。
特に注目されているのは、「大の里が先に土俵外に足をついたように見えたのに、なぜ**物言い(ビデオ検証も含めた協議)**が行われなかったのか?」という点である。
この記事では、問題となった取り組みの流れを整理しつつ、物言いがつかなかった背景と、今後の相撲界が抱える課題について深堀りしていく。
■ 勝敗を分けた一番の流れ
まずは取り組みを振り返ろう。
両力士が立ち合いでぶつかり合った後、大の里が得意の右四つの体勢に持ち込む。上体を低く構え、力強く前に出た横綱は、安青錦の土俵際での反撃をものともせず、勢いそのままに寄り切りで勝利を収めたと判定された。
実況・解説も一時は納得した様子だったが、リプレイ映像を見た視聴者の間で違和感が広がった。SNSや相撲系掲示板では以下のようなコメントが飛び交っている。
- 「スローで見ると、大の里の左足の甲が土俵の外についたように見えた」
- 「安青錦の体はまだ空中だったのでは?」
- 「これは“同体”に近い判定では?」
つまり、大の里の“落ち”が先に見えたという指摘が多く、「物言いがつかないのはおかしい」という意見が多数派となっている。
■ そもそも「物言い」とは?どんなときに出るのか
相撲の取り組みにおける勝敗判定は、土俵上の行司が行う。しかし、行司の判定に対し、**土俵下に控える審判委員(5名)**のうち誰か一人でも異議を唱えた場合、「物言い」がつく。
物言いがついた場合、審判団による協議が行われ、必要であればVTR(スロー映像)を確認し、最終的な判定を下す。
つまり、物言いが発生しなかったということは、審判5名全員が「行司の判定は正しかった」と認識したということであり、これはある意味“満場一致の決着”である。
しかし今回のように「映像では微妙に見える」ケースでは、「物言いがあってしかるべき」という見方が強い。
■ “死に体”という概念が左右する判定
今回、安青錦の体が宙に浮いた状態でありながら、大の里の足が土俵外に触れたようにも見えた。この場面においては、「どちらが先に土に触れたか」が焦点となるはずだ。
ところが、相撲の世界にはもう一つ重要な判定基準がある。それが、「死に体(しにたい)」という考え方だ。
死に体とは、たとえ体の一部がまだ宙にあっても、その力士が「既に勝負権を失った状態」と見なされることを意味する。たとえば、体勢が完全に崩れていて反撃が不可能な場合や、明らかに土俵外に出るしかない姿勢である場合、その力士は“先に負けた”と判断される。
今回の取り組みで物言いがなかったのは、安青錦が“死に体”と判断された可能性がある。つまり、土俵外に浮いている時点で体勢を立て直せないと見られたため、たとえ大の里の足が先に落ちていても、それ以前に安青錦の“敗勢”が確定していたというロジックだ。
■ 審判団に求められる「納得性」と「説明責任」
とはいえ、このような“死に体判定”があった場合でも、近年のスポーツ観戦者が求めるのは「結果の透明性」と「判断理由の明確な説明」である。
今回の取り組みでは、非常に僅差であったにも関わらず、協議や説明が行われなかったことに対する不満が多く見られた。
SNS上には次のような投稿もある:
「解説者も少し言葉を濁していた。明確な説明があればここまで荒れなかった」
「リプレイ映像では十分に物言いレベル。なぜ確認すらしないのか?」
スポーツにおける誤審や疑惑判定は、観る側の信頼を損なうリスクをはらんでいる。特に相撲のように1勝の重みが極めて大きい競技では、なおさら慎重な判断と説明が求められる。
■ 今後の課題:ビデオ判定の拡充は必要か?
近年、他のスポーツ競技ではビデオ判定(VAR、チャレンジ制度など)の導入が当たり前になってきている。
相撲でも、2018年ごろから一部の取り組みにVTR判定が導入されているものの、あくまで審判の補助的判断材料であり、すべての取り組みにおいて強制的に活用されるわけではない。
今回のような重大な勝敗に関わる場面では、ビデオ判定を積極的に活用し、必要であれば**場内アナウンス等を通じて「このような理由で物言いは不要だった」**と説明を加えるべきだという声もある。
伝統と技術の調和をどう実現するか――それが、今後の相撲界に突きつけられた課題だ。
■ 安青錦の精神力と実力に注目
誤審か否かの議論は続くが、取り組み全体を通して言えるのは、安青錦が堂々たる内容の相撲を取っていたということだ。大関昇進に向けて重要な一番で敗れはしたものの、その内容は決して引けを取るものではなく、多くの相撲ファンが健闘を称賛している。
今場所で昇進が叶わなかったとしても、初場所での再チャレンジは十分に期待できる。むしろ、この一番をバネにして精神的にも一回り成長するきっかけになるだろう。
■ まとめ:相撲の判定に必要な“納得のプロセス”
今回の「大の里 vs 安青錦」の一番をめぐる議論は、単なる勝ち負けではなく、「なぜその判定になったのか?」というプロセスの不透明さに対する不満だ。
【ポイントを整理】
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| 勝敗 | 大の里が寄り切りで勝利と判定 |
| 問題点 | スロー映像で大の里の足が先に落ちたように見えた |
| 審判の判断 | 安青錦は「死に体」として処理された可能性 |
| ファンの声 | 「物言いすべきだった」「誤審では?」との声多数 |
| 改善点 | 映像判定の拡充、判断理由の説明、透明性の確保 |
相撲は国技であり、日本人の精神文化と深く結びついている伝統競技だ。しかし同時に、時代の変化に合わせた制度的なアップデートが求められるフェーズに差しかかっている。
勝者の栄光と敗者の悔しさ、そのいずれもが納得のいく形で伝わる土俵であってほしい――そう願うファンの声に、相撲界はどう応えていくのか、注目していきたい。

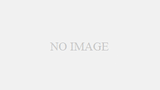
コメント